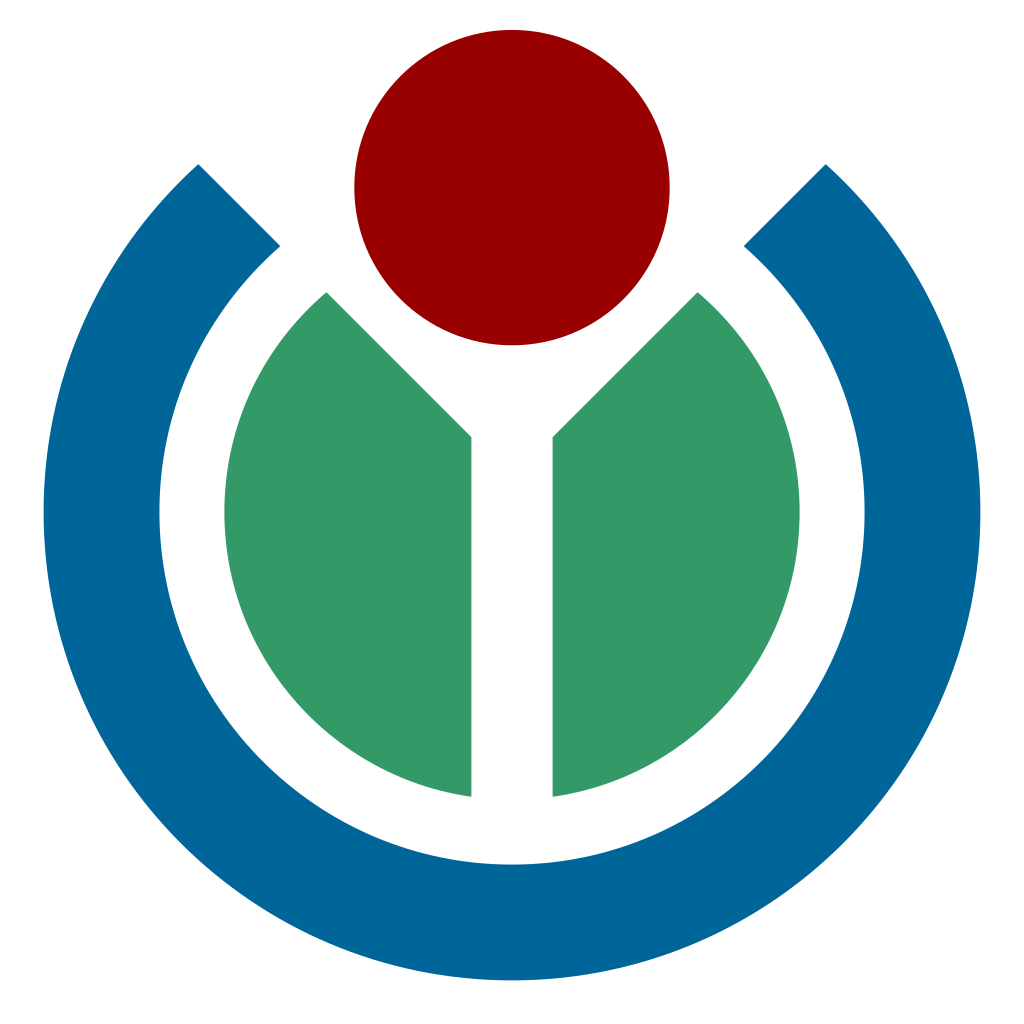稲門ウィキペディアン会の Eugene Ormandy です。本稿では、高山正也、岸田和明が編集した図書『図書館概論』におけるウィキペディアに関する記述をピックアップし、コメントします。

書誌情報
- 高山正也, 岸田和明 編著ほか. 図書館概論. 改訂, 樹村房, 2017.8, (現代図書館情報学シリーズ ; 1). 978-4-88367-271-4. https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I028498722
なお、この書誌情報はNDLサーチの「引用文(参考文献注)を生成」メニューより作成しました。
ウィキペディアに関する記述
第7章「将来の展望」の第1節「コンピュータの発達と図書館」における第4項「情報探索行動の変化と図書館」に、ウィキペディアに関する記述が登場していました。以下、少々長くなりますが引用します。
以上のコンピュータやネットワークの発展や、それに伴う情報資源やメディアの変化は、単なる技術的な側面だけでなく、人々の情報探索行動 (information seeking behavior) 自体にも抜本的な変化をもたらした。サーチエンジンを使えば、図書館のレファレンスサービスを活用しなくとも、さまざまな事柄を調べることができるし、すでに紹介した青空文庫のような無料で読める書籍もインターネット上に存在している。
このような利便性の向上は、人々の情報探索行動における「図書館」の相対的な重要性を低い位置へとシフトせざるをえない。この傾向は特に学術情報を主に取り扱う大学図書館において顕著である。例えば、上で述べたように、その図書館が電子ジャーナルを提供しているならば、その対象雑誌に関してはわざわざ来館しなくとも、研究室等のパソコンから論文のPDFファイルをダウンロードできる。また、学生がレポートを書く場合、かつては参考図書コーナーの辞典やハンドブック類で下調べをしていたのが、今では、ウィキペディア (Wikipedia) などを利用して容易にそれを済ますことも可能である。これらのいずれの場合でも、情報探索行動の中で、図書館という存在は消失している。もちろん、電子ジャーナル等の閲覧・利用については、契約・アクセス許可の点で図書館は本質的な役割を果たしているが、多くの利用者の視界からは図書館自体の像(イメージ)はうすくなりつつある。また下調べでのウィキペディアなどの利用に関しては、同時に質の悪い情報も存在するというインターネットの本質的な問題はあるものの、調べることのできる範囲の広大さ・検索の容易さの点では、伝統的な図書館が提供できる手段を凌駕している。
前掲書、159-160ページ。
感想
個人的には「ウィキペディアの長所についても言及してくれているのは嬉しいけど、ちょっと褒めすぎかな」と感じました。特に「調べることのできる範囲の広大さ」という記述については、「ウィキペディアで調べることのできる範囲は著者が想定しているほど広くはないから、伝統的な図書館が凌駕する点も多くあるんじゃないかな」と感じたので、以下3点補足します。
1つ目は、方針上ウィキペディアに立項できない主題についてです。ウィキペディアには「独立記事作成の目安」というガイドラインが存在し、いわゆる一次資料しか存在しない主題や、速報的な主題は基本的には立項できません。もちろん、これらの理念をどの程度厳格に運用するかについてはウィキペディアンたちが侃侃諤諤の議論を行なっているため、例外は存在します。
2つ目は「方針上ウィキペディアでの立項は可能だが、人手不足のため立項されていない主題」についてです。いうまでもなく、そのような事例は山のように存在します。例えば「英語版ウィキペディアでは立項されているが、日本語版にはない主題」は数多くありますし、ウィキペディアンたちのSNSに目を通せば「○○の記事がまだ立項されていないんだね」といったコメントを多々読むことができます。また、私もオーボエ愛好家として「こんな有名な奏者の記事がないのか」と愕然とすることがままあります。
3つ目の補足は、ウィキペディアの言語版ごとの充実度の違いについてです。ユーザー数の少ない言語のウィキペディアは、往々にして内容があまり充実していません。また、そもそもウィキペディアが存在しない言語もあります。このような少数言語とウィキペディアの関係については、下記のブログ記事が参考になると思うので、興味のある方は是非ご覧ください。
- Amrit Sufi (30 May 2023) “Angika: Creating and sustaining a Wikipedia in an underrepresented language” Diff.
- Tochiprecious (7 July 2023) “Wikitongues selects 21 Language Champions to preserve endangered tongues” Diff.
- Srishti Sethi (18 April 2024) “Language and Internationalization/Newsletters/3” Diff.
日本語版ウィキペディアは、他言語版に比べて充実しています。それは、日本語版ウィキペディア「Wikipedia:全言語版の統計」を見ればわかります。本稿を執筆している2024年5月末時点で、日本語版ウィキペディアの記事数は全言語版中第13位なのです(ちなみに1位は英語です)。今回取り上げた図書『図書館概論』における「ウィキペディア」に関する記述は、おそらく「日本語版ウィキペディア」のみ、もしくは日本語版と英語版のみを想定としていると予想されますが、これはやや視野狭窄ではないかなと感じてしまいました。教科書として概論を紹介するという本書の性格上、仕方がないことかもしれませんがね。
まとめ
図書『図書館概論』における「ウィキペディアがあるから学生が図書館に来てくれない」という趣旨の指摘を引用し、「いやそもそもウィキペディアってそこまで充実してないし、言語版ごとに状況はだいぶ違いまっせ」とコメントしました。もちろん、「本論はあくまで『ウィキペディアがあるから図書館は行かなくていいや』という各人の行動基準を指摘したものであり、実際にウィキペディアが充実しているか否かは関係ない」と言われればそれまでなのですが、実際にウィキペディアを編集し、ウィキメディア・プロジェクトを活用した少数言語保護活動に取り組んでいる人間として少し違和感を覚えたので、野暮を承知でダラダラと書いてみました。

Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?
Start translation