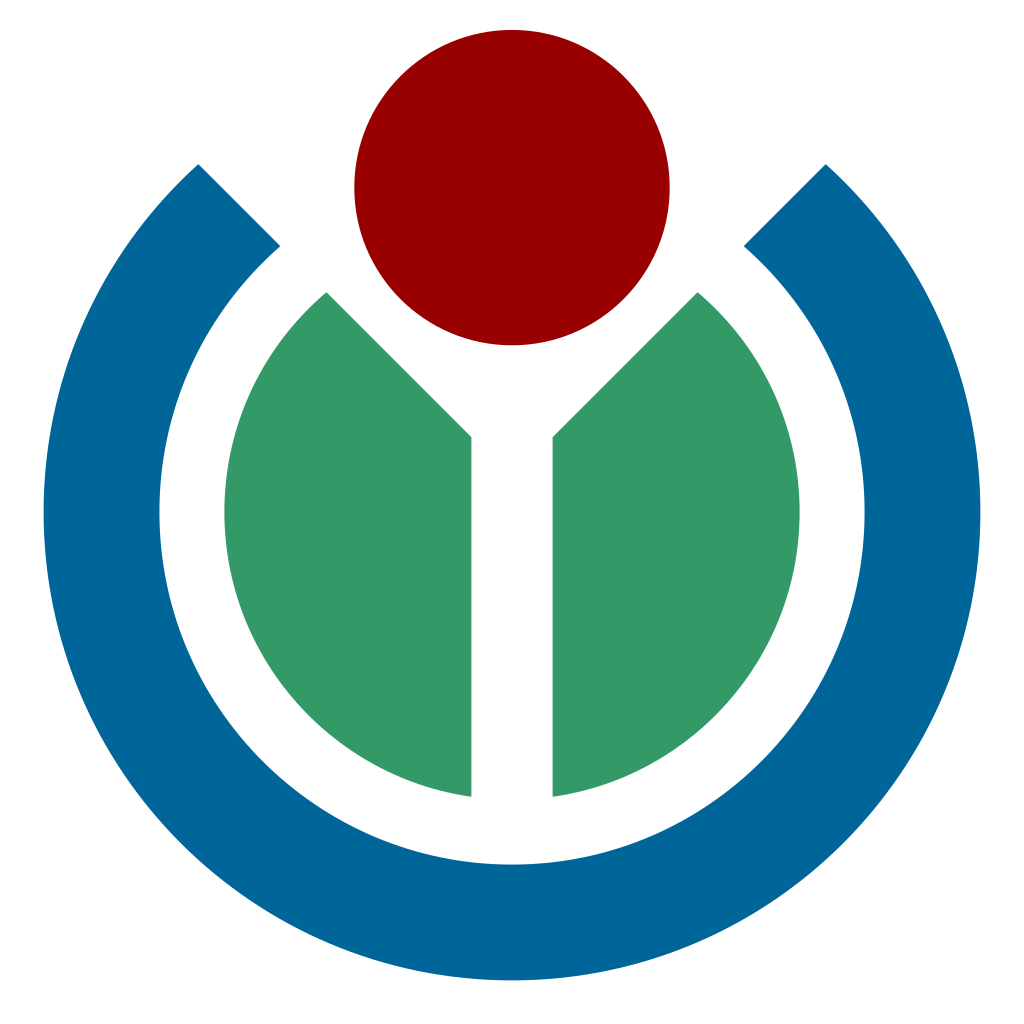人生はたいていの場合、日常のルーティンを前に進めながらも、もっと何かを切望することがある。僕はウィキマニア2024の助成金に初めて応募したけれど、落選してがっかりした。結果のEメールを受け取った時は呆然として、ウィキマニアに行くのはすっかり諦めた。しかし、失敗は終着点でないことがすぐにわかった。ウィキマニア助成金委員会から断られた後に、僕はCIS-A2kに選ばれたんだ。この経験は、希望には回復力があり、いつも生きていることを再確認させてくれた。
パスポートとヴィザ
その時僕はパスポートを持っていなかったので、すぐに申請して届くのを待っていた。ヴィザ取得プロセスについては、CIS-A2kチームのNitesh ji、Nivas ji、Madini ma’am、そしてPavan jiが役に立つ案内をしてくれて、必要書類を取り寄せたり、内容を正しく記入するのを手伝ってくれた。何人かの申請者がヴィザを取得できなかったと聞いたので、僕は心配になった。しかし希望は捨てなかった。申請から17日後、僕はやっとヴィザを取得し、希望は死なないことを実感した。
旅行

それは楽しく興奮に満ちた旅だった。僕の最初の海外飛行は、僕の夢にほんとに翼をつけてくれた。デリーのインディラ・ガンディー国際空港を出発する時は、バングラ・ウィキソースのSujata ma’amと、サンタル語版ウィキペディアのRamajitと一緒で、旅行中は実に楽しかった。Sujata ma’amは旅行ガイドのようで、Ramajitは双子の兄弟みたいだった。フランクフルト空港はとても広大で、もし彼らがいなかったら僕はきっと迷子になったに違いない。僕たちは一緒に、夜遅くについにポーランドのカトヴィツェに着いた。疲れてお腹がすいていたけれど、それよりもスリリングな旅行が思い出され、それを忘れないように何枚か写真を撮ったんだ。
アッサムの香り

いろいろ興奮することはあったけど、ウィキマニアでの僕の一番の目的は、小さいけれど意義深いアッサムの一片をグローバルな舞台に紹介する事だった。僕のことだけでなく、僕の文化のエッセンスを共有したかった。一番最初の日に、僕は自分のルーツであるアッサムの伝統衣装を身につけてアピールした。それと共に、アッサムの代表的菓子、美味しいピタを会場のスイーツテーブルに提供した。また僕は二つのジャピ、文化の象徴としてよく使われるアッサムの伝統的な帽子を持ってきたので、工芸品収集家のためにそれを並べた。
多くの人にとって、こうしたやり方は国際的な大イベントの中では些細なものにみえたかもしれない。でも、僕みたいな田舎の少年にとってそれは、ものすごく大きな意味があった。こうした品々を地球半周かけて国際イベントに持ち込んだのは、食べ物や工芸品を共有するだけでなく、僕の故郷、僕の文化、僕のコミュニティを、多様な背景を持つ人たちに評価してもらうことだった。僕はアッサムの精神を運び、それを世界に贈り物として捧げたんだ。
嬉しかったのは、2日目にはもう、ピタが全部無くなっていたことだ。それは小さなことだけど、僕の文化が受け入れられたことを知って胸がいっぱいになった。この単純な共有で僕は、どんなに遠くへ行っても、皆自分のルーツを携え、小さな心を込めたジェスチャーこそが、心に残る印象を与えることを知った。
世界に橋を架ける:旅からの学び

全体の手配は僕にとって素晴らしい驚きだった。4日間の日程で約13のセッションに参加したけれど、どれも新し視点と価値のある知識を与えてくれた。一番心をとらえたのは、異なる国々から来て言葉も違う人々が、自分たちの文化遺産を守るのに誇りをもってボランティア活動をしていることだった。世界中から集まった人々が、ウィキメディアを通じて自分たちのルーツを守り広めるという同じ目標に向かっているのを見たのはほんとに感動した。
他の人たちがそれぞれの言語や伝統を祝うのを見ながら、僕は自分の母語に深い誇りを感じた。それはグローバルコミュニティにおいて僕たち一人ひとりのアイデンティティの重要性を強く思い起こさせるものだった。セッションの枠を超えて、僕は新しい友達を作り、異なる背景の人たちと会話を交わし、僕たちが共有する使命についての意見交換をより深く理解する機会を得た。
コレクターとして、僕はいろいろな国々のコインや切手をワクワクして集め―それは小さいけれど僕が作ったグローバルなつながりだった。だけど僕の心をほんとに温かくしたのは、インドのウィキメディアンたちの力強い姿を見たことだった。彼らの存在は心地よいだけでなく力強く、カトヴィツェがまるで故郷の様に感じるほどだった。こんなにたくさんの同国人を国際的舞台で見ることで、僕は誇りと自国の力強さを感じた。
この4日間は単なる学習経験以上のものだった。それは文化的多様性、コラボレーション、世界の知識を保存するという共通の目標に参加することだった。僕は新しい知識を得ただけでなく、新たな目標と帰属意識を持ってその場を後にした。
一杯のアッサムティー

前に書いたように、長時間飛行の後で、翌日遅くにやっとホテルにたどり着いた。ひどく疲れてお腹がすいていたので、僕は旅行者の定番、ハンバーガー、チキンケバブ、そしてサラダを食べようと思った。でも異国の街でそれを思うと、何を食べるか、何が僕の胃に合うのか迷っている不思議なバスケットを持って料理番組に出ている気分になってきた。
翌朝、豪勢なビュッフェが待っていたので、王宮の祝宴に間違って入り込んだのかと思ってしまった。興奮のかわりに、不安に襲われた。僕の皿に何を取ったらいいんだろう?スパイシーなインド料理に慣れている僕の胃は、この冒険に耐えられるだろうか。注意深く眺めてから、僕はなんとなく馴染んでいると思えるいくつかをみつけた。
でも一番がっかりしたのは、シンプルな紅茶が無かったことだった。家に帰れば、紅茶は単なる飲み物でなく、カップに入った温かいハグなんだ。ほっとしたことに、いろいろなお茶の中にダージリンとアッサムのティーバッグをみつけた。隠された宝物を見つけたように、それを10個ほどポケットに入れた時、僕の心臓は小躍りした。最初の一杯のアッサムティーは最高で、料理がカオスになっている中で故郷の味がした。
それでも、異国の料理に慣れるのは難しいのがわかった。3日間お米-僕の主食-に出会わなかったので、母さんに電話で「ママ、3日もお米を食べてないんだ!」と伝えた。母さんは笑って、「もしわかっていたら、クモール・ソール(少しのお湯をかければ食べられる軟飯)をスーツケースにいれてあげたのに」と言った。
最終日、「アジア」ランチが出てきたが、それはポーランド風にアレンジされたもので、マイルドで僕が大好きなスパイスが欠けていた。だけど、他の選択肢は無かった。僕はありあわせのものを食べた。この慣れない食べ物の海を航海するのは挑戦だったが、しかしそれは僕に、食品が単なる栄養補給以上のものだと教えてくれた。たとえスパイス抜きのビュッフェでやり過ごすとしても、それは僕たちのルーツや文化と結びついているんだ。

Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?
Start translation