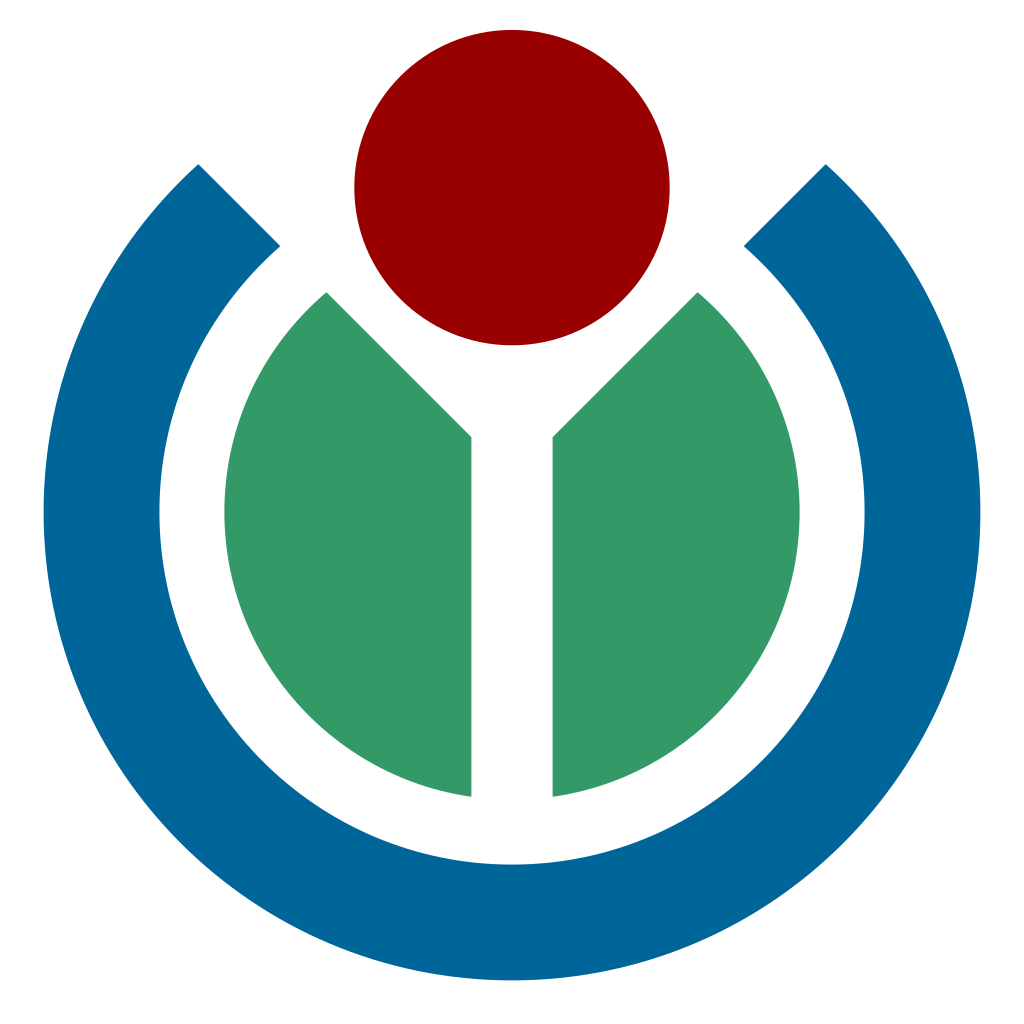2022年12月11日、稲門ウィキペディアン会は、ウィキペディア編集者3名によるオンライン対談を実施した。参加したウィキペディア編集者は Swaneeさん、Kinstoneさん、Eugene Ormandy の3名である。本稿では、その模様を詳述する。
登場人物紹介
Swanee
2009年より活動。編集分野はバレエ、郷土史、動物など。良質な記事を20本以上作成する超優良執筆者。主な記事は [[下山千歳白菜]], [[奥澤神社]], [[ハチ (ヒョウ)]]など。
Kinstone
2020年より活動。編集分野はバレエ、舞台芸術など。主に、バレエの演目や振付家の記事を執筆している。主な記事は [[白鳥の湖]], [[トウシューズ]] など。
Eugene Ormandy
2018年より活動。編集分野はクラシック音楽の演奏家、喫茶店など。稲門ウィキペディアン会を主催。主な記事は [[アルトゥール・ニキシュ]], [[どん底 (飲食店)]] など。本稿執筆者および対談司会。
対談
Eugene Ormandy
本日はお集まりいただきありがとうございます。今回は、ウィキペディアに関する5つのテーマについてお話しできればと思います。よろしくお願いします。
テーマ1. ウィキペディア編集を始めたきっかけ
Eugene Ormandy
1つ目のテーマは、ウィキペディア編集を始めたきっかけについてです。まずは私からお話ししますね。
私がウィキペディア編集を始めたきっかけは、2018年12月に北村紗衣さん(さえぼーさん)が武蔵大学で開催した「研究・教育関係者向けウィキペディア記事の書き方講習会2018」です。この講習会には、図書館関係者の知り合いに誘われて参加しました。
講習会で基本的な編集スキルを身につけ、少しずつ記事を書くようになりました。講習会の前からウィキペディアの存在自体は知っていたのですが、まさか自分が編集をするようになるとは思ってもいませんでした。
Swanee
私がウィキペディアのことを知ったのは2006年ごろですが、編集するようになったのは2009年です。とあるバレエダンサーについてのウィキペディア記事を書きたいと思い、独学で編集スキルを身につけました。
Kinstone
私がウィキペディア編集を始めたきっかけは、北村紗衣さんがウィキペディアとシェイクスピアについて講義をしている、高校生向けのYouTube動画を観たことです。2019年のことですね。
動画では、北村さんが武蔵大学で実施している「英日翻訳ウィキペディアン養成セミナー」というゼミが紹介されており、自分が大学生だったら受講していたのになあと思いました。
2020年になって、ウィキペディアで何かの調べ物をしていた際、ふと「大学生ではなくてもウィキペディアは編集できるよな」と思い、編集を始めました。編集方法は、北村さんが「英日翻訳ウィキペディアン養成セミナー」のプロジェクトページにまとめている各種マニュアルを読んで学びました。
Eugene Ormandy
三者三様で面白いですね!
テーマ2. どのように編集スキルを身につけたか
Eugene Ormandy
2つ目のテーマは、ウィキペディアの編集スキルをどのように身につけたかについてです。
先述のとおり、私は武蔵大学での講習会で編集方法を学びました。ただし、講習会で教わったのはビジュアル編集のやり方だったので、ソース編集については、自分で学ぶ必要がありました。テンプレートやインフォボックスなど、基本的にはソース編集モードでしか編集できないものも多いですからね。
ソースの書き方は、他のウィキペディア記事を見ながら学びました。また、自分が書いた記事を他の人が修正・加筆してくれた際、その差分を確認してカテゴリやテンプレートの書き方を学びました。初めて作成した [[名曲喫茶ライオン]] の初稿を見返すと、足りないところだらけで冷や汗が出ます。
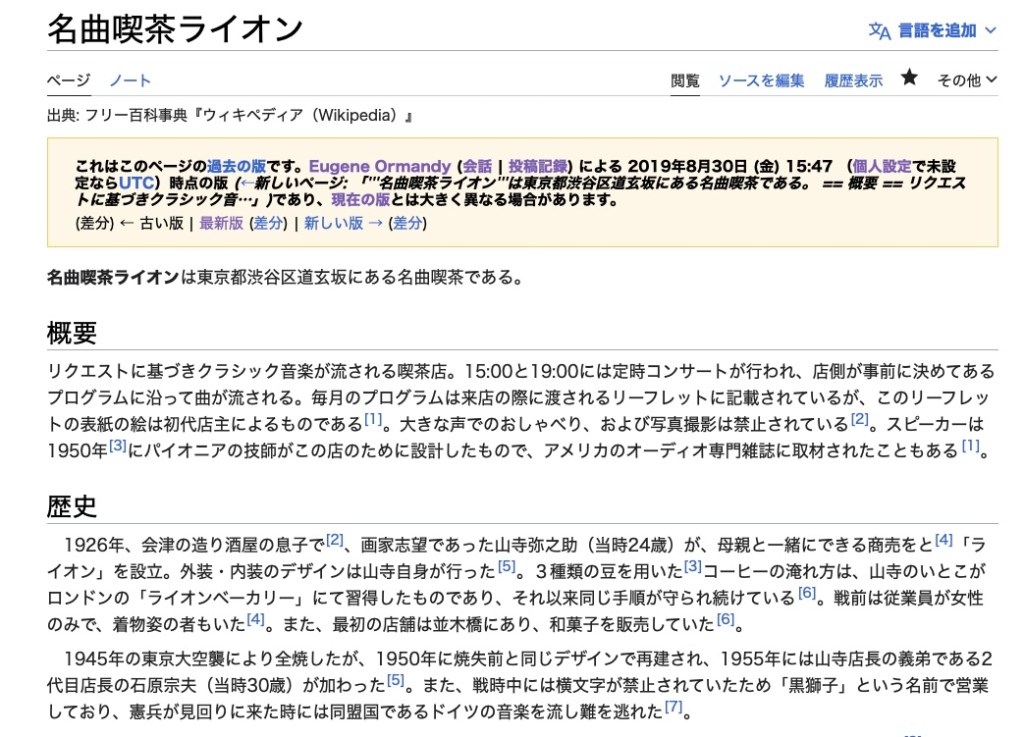
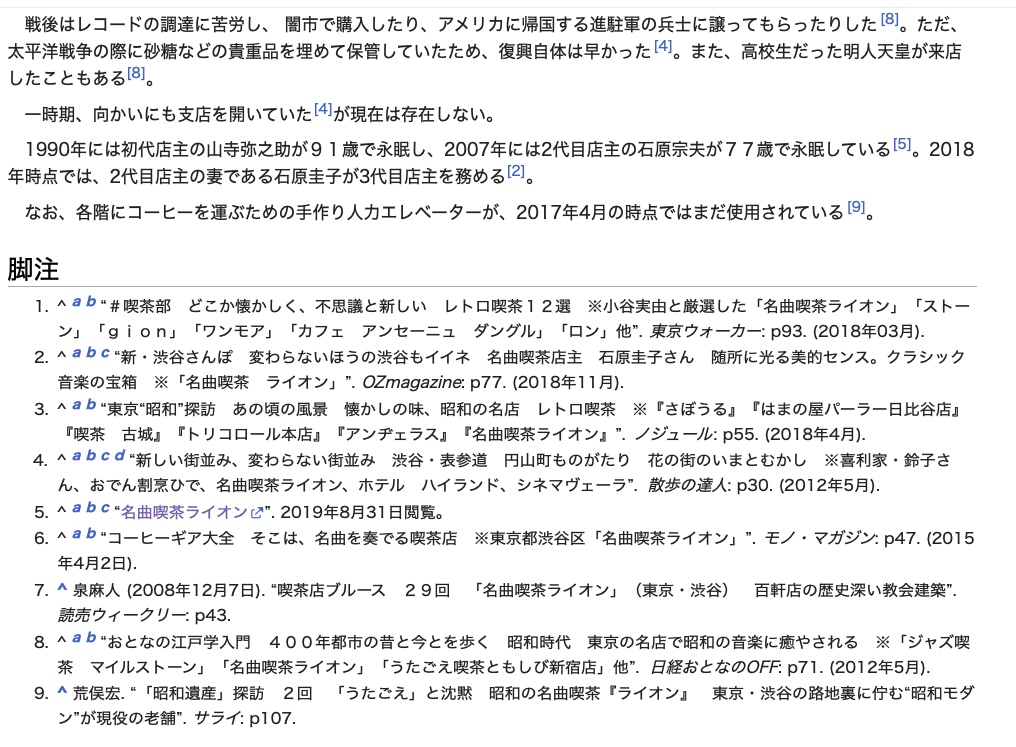
Swanee
私は独学で編集スキルを身につけました。私も Eugene Ormandy さんと同じく、自分の記事が他の人に修正された時の差分などを確認して、様々な記法を学びました。また、私はオリンピック選手の記事を何本か書いているのですが、新たに記法を学んだ時は、それらの記事に活かしました。
なお、私が参加した時はビジュアル編集機能が存在しなかったので、必然的にソース編集を学ぶことになりました。ビジュアル編集機能が登場した際、知人の勧めもあり試してみたのですが、私には合わなかったので、今でもソースで編集しています。
Kinstone
私は北村さんの「英日翻訳ウィキペディアン養成セミナー」のページに掲載されていた各種マニュアルを読んで学んだので、「書きながら覚える」というより、初めからある程度体系的に編集スキルを身につけられたのではないかなと思います。
最初に記事を執筆したときは、北村さんのゼミの受講生が作成した記事のソースコードを印刷し、それを真似しながら書いていました。このときソース編集で一通りの編集方法を覚えたので、その後もビジュアル編集機能は使っていません。
Eugene Ormandy
これも三者三様で面白いですね。個人的には、Swaneeさんの「新たに学んだ記法をオリンピック選手の記事に活かしていた」という姿勢にシンパシーを感じました。というのも、私も初心者時代に何本か書いた名曲喫茶の記事において、同じことをしていたからです。
Swanee
似たようなトピックの記事を何本も書くと、構成もある程度わかってきて余裕も生まれますし、新たに学んだことを実践しやすくなりますよね。
テーマ3. どんな記事を編集しているか
Eugene Ormandy
3つ目のテーマは、どんな記事を編集しているかについてです。
私はクラシック音楽の演奏家や、喫茶店の記事を編集しています。ウィキペディアを始める前からある程度知っている分野なので、比較的スムーズに記事を作成することができます。
一方、前提知識が全くない分野の記事を編集することもあります。具体的には、[[フルーツサンド]] や [[タハン山]] ですね。これらの記事は、ウィキペディア編集イベントをきっかけに着手しました。前提知識が全くないものについて書くときは、調査や執筆の方法をきちんと考える必要があります。自分の調査スキルを向上させるためにも、こういった記事は定期的に作成したいですね。
基本的に手を出さないと決めている分野もあります。具体的には、英語記事の翻訳と、楽曲記事の編集です。指揮者の記事を書いているのだから、楽曲の記事も書けるだろうと友人に言われたことがありますが、記事の構成などを考慮すると、これらは大きく異なると感じます。指揮者の記事は人物の来歴が中心になるのに対し、楽曲の記事は上演史や楽曲構成などを盛り込まなければいけませんからね。
Swanee
私は主にバレエ、動物、郷土史の記事を編集しています。
バレエについては、ダンサーの記事も編集しますし、作品や振り付けに関する記事も編集します。基本的なテンプレートさえ作ってしまえば、あまり迷わずに編集できますね。ただし、ダンサーについての記事を編集するときは「私生活」の章に困ることが多いです。私生活についての情報がほとんどない方もいれば、その逆の方もいるので。
動物の記事については、初めは翻訳からスタートしたのですが、その後日本語の資料を用いて日本の動物についての記事を編集するようになりました。また、郷土史については、ウィキペディアタウンというイベントに参加するようになってから編集するようになりました。
たまたまウィキペディアをブラウジングしていて見かけた事柄や、図書館にて本棚をぶらぶらしている中で気になった本を使って、ウィキペディア記事を編集することもあります。例えば「コメットハンター」として知られる [[羽根田利夫]] の記事ですね。この記事は良質な記事に選出されました。
手を出さないと決めている分野は、声優や政治家ですね。いわゆる「荒らし」によるイタズラがしばしば発生するので。
Kinstone
私も Swanee さんと同じく、バレエや舞台に関する記事を編集しています。
最初は北村さんが作成された「翻訳候補記事の一覧」のリストからピックアップして翻訳をしていたのですが、次第に資料を自分で集め、日本語で記事を書くようになりました。また、当初は新規記事の立項が多かったのですが、今はバレエに関する重要なトピックで、分量が不十分な記事に加筆することが多いです。
手を出さないと決めている記事は、[[バレエ]] のような包括的なトピックです。見る人が多いページである分、いつか修正しないとなと思うんですけどね……。
Eugene Ormandy
気持ちはよくわかります……。私も [[クラシック音楽]] の記事を編集するのは怖いですね……。
Swanee
同感です。
Eugene Ormandy
ところで 、バレエの記事を編集する際、クラシック音楽のことも書かなくてはいけないケースって結構多いですよね?
Swanee
そうですね。ジョージ・バランシン関連の記事を編集するときは、どうしてもクラシック音楽について調べる必要があります。以前、[[シンフォニー・イン・C (バレエ)]]という記事を書いた時は、ジョルジュ・ビゼーの交響曲について調べました。
Eugene Ormandy
いい曲ですよね〜!
Kinstone
私は知識不足で、音楽学的な記述には触れられませんね……。得意な方に加筆していただければと思います。
Eugene Ormandy
実はクラシック音楽記事を編集するウィキペディアンからしても、バレエに関わるトピックは少し書きづらいなと思うんですよね。振付や上演史について調べないといけないですし。あと、オペラとバレエはなんとなく壁があるように感じます。バレエを指揮することの多い指揮者は「バレエ専門」のように言われることが多いですしね。
Kinstone
バレエの指揮者って、クラシック音楽系ウィキペディアンも、バレエ系ウィキペディアンも書きづらい存在なのかもしれませんね。
Eugene Ormandy
今度協力して何か書きましょうか……笑
テーマ4. ウィキペディア編集のモチベーションは何か
Eugene Ormandy
4つ目のテーマは、ウィキペディア編集のモチベーションについてです。
私のモチベーションは間違いなく「インフラを作れること」ですね。自分の知識が人の役に立つことに、非常にやりがいを感じます。
[[デジレ・デフォー]] という指揮者の記事には、特に思い入れがありますね。英語資料を活用することで、デフォーについての(恐らく)最も詳しい日本語資料を作成できたからです。また、国立国会図書館サーチでヒットしない日本語資料を、参考文献として記載できたことも、誇れることの一つです。例えば国立国会図書館サーチで「デジレ・デフォー」と検索しても、デフォーのウィキペディア記事の参考文献欄にある『新世代の指揮者8人』や『アメリカのオーケストラ』という資料はヒットしません。これらの資料は、図書館の本棚にある本をひとつひとつチェックした結果、発見したものです。[[デジレ・デフォー]] というウィキペディア記事は、インフラとして価値の高いものになったのではないかなと自負しています。
また、自分の調査・執筆スキルが向上することもモチベーションの一つですね。ひたすらレポートを書いていた学生時代に「漫然と本を読むだけでは不十分で、アウトプットをしないと結局知識は身につかないし、スキルも上がらないな」と痛感したので、自分のためにもウィキペディア編集というアウトプットは続けたいですね。
Swanee
自分の記事が翻訳されたときは嬉しいですね。ありがたいことに、私が関わった記事は今まで英語、ロシア語、ウクライナ語、韓国語、ドイツ語などに翻訳されています。また、英語、韓国語、およびインドネシア語に翻訳された[[中川の箒スギ]]はインドネシア語版と韓国語版の「良質な記事」に選出され、特に嬉しかったです。
Kinstone
私のモチベーションは主に2つですね。
1つ目は「情報をまとめ直すことが好きだから」です。私も Eugene Ormandy さんと同じく、本を読むだけだとあまり頭に残らないなと思うタイプで、自分なりのレジュメを作りたくなるんですよね。2つ目は純粋に、バレエや舞台といった、自分が好きなものに関われるのが嬉しいからです。
Eugene Ormandy
余談ですが Kinstone さん、タスクをこなすときに作業表やレジュメを事前に作成するタイプですか……?
Kinstone
そうです!
Eugene Ormandy
仲間です!ちなみに Swanee さんはいかがでしょう?
Swanee
全くもって同じです笑
テーマ5. 今後の展望
Eugene Ormandy
最後のテーマは「今後の展望」です。
私は今後もクラシック音楽の演奏家に関する記事をチマチマと作成できるといいなと思っています。また、ありがたいことに大宅壮一文庫などの専門図書館でウィキペディア編集イベントを開催できるようになったので、これを継続させていきたいですね。
Kinstone
細く長く続けていければなと思っています。自分の性格にあった趣味ですからね。
今後の課題は「少しずつ編集できるようになること」と「幅を広げること」です。今はまとまった時間を確保して一気に編集するスタイルなのですが、効率を上げるためにも、今後は少しずつ下書きをブラッシュアップするスタイルにしたいですね。あと、Swanee さんをはじめ、イベントでお会いするウィキペディアンはみなさん博識で執筆範囲も広いので、私もそうなりたいなと思っています。
Swanee
今後も動物やバレエに関する記事を編集していきたいですね。あと、文学作品の記事があまり充実していないので、整備したいなとも思っています。芥川賞候補作になった作品も、記事がないことが多いですからね。
Eugene Ormandy
本日はお集まりいただきありがとうございました。とても楽しかったです!

Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?
Start translation