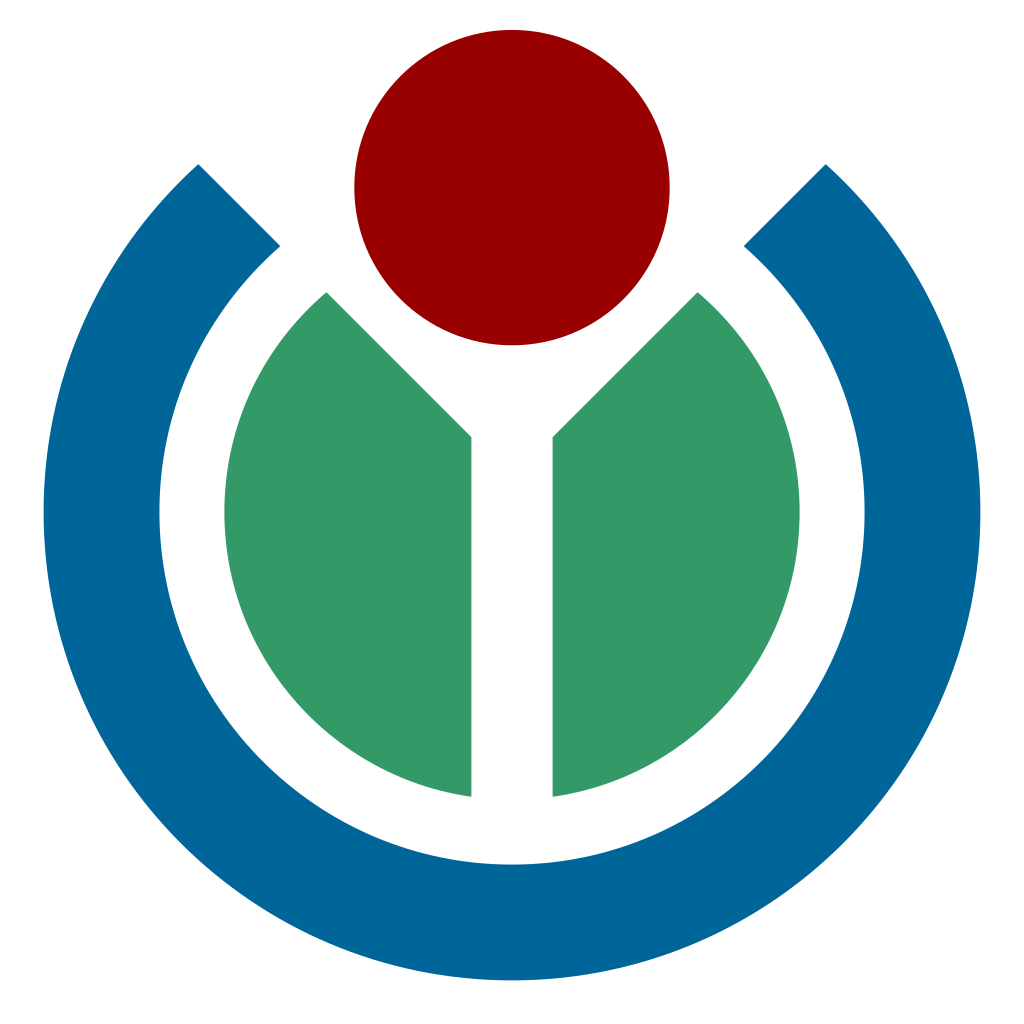2023年5月、ウィキペディアンの逃亡者さんにインタビューを行いました。インタビューでは、逃亡者さんが新規立項したウィキペディア記事 [[蓬莱屋 (とんかつ店)]] の調査・執筆方法について伺いました。なお、インタビュー時に参照した版は 2023年5月19日 (金) 23:24 (UTC) 版です。

執筆の経緯
Eugene Ormandy
本日はよろしくお願いします。まずは [[蓬莱屋 (とんかつ店)]] を執筆した経緯について教えてください。
逃亡者
2023年4月に神奈川県で開催されたウィキペディア編集イベント「第9回 Wikipedia文学『小津安二郎』」を機に着手しました。このイベントは、映画監督の小津安二郎に関するウィキペディア記事の充実を目指していました。そこで、小津がよく通ったとんかつ屋である蓬莱屋の記事を立項しました。
なお、現地には行けなかったので、イベントはオンラインで参加しました。ところで、このイベントには Eugene さんも参加されてますよね。
Eugene Ormandy
はい。私は現地で参加しました。とても楽しかったです。なお、その時の体験記は、ウィキメディア財団のブログ Diff に寄稿しています。
逃亡者
そちらの体験記は拝読しました。私と Eugene さんの共通点は、はじめに「ウィキペディア記事 [[小津安二郎]] は編集しない」と決めたことですね。
まず真っ先に決めたのは「 [[小津安二郎]] というウィキペディア記事には絶対に手を出さない」ということ。既に内容が充実しているからでもありますが(参照した版は 2023年4月16日 (日) 10:57 (UTC) 版)、そもそもこのような「書くべきことが大量にある / 何を書かないかの判断が重要であるトピック」については、知識のあるウィキペディアンが伝記などを用いて体系的に編集するべきだと私は考えています。少なくとも、全く予備知識のない私が、イベントの時間内にどうこうできる代物ではありません。
Eugene Ormandy「よく知らない映画監督に関するウィキペディア記事を堂々と編集する方法 : 第9回ウィキペディアブンガク体験記」より引用。
ただし、「既存の記事に加筆をする」と決めた Eugene さんとは異なり、私は新しい記事を立項することにしました。加筆よりも新規立項の方が好きだからです。また、「文学や映画の記事は他のイベント参加者が編集するだろうから、それ以外のものを書こう」と考えました。どうも私は、他の人が歩かない道を歩くのが好きなようです。
次に決めたのは「新規立項はしない」ということ。ウィキペディアは新しく記事を立項することも可能ですが、既存の記事に加筆をすることもできます。私はどちらも経験したことがありますが、基本的には加筆の方が楽です。そのため、予備知識がない状態で、イベントの限られた時間内に有意な編集をすることを目標とした場合、加筆の方が実現可能性が高いと判断しました。
Eugene Ormandy「よく知らない映画監督に関するウィキペディア記事を堂々と編集する方法 : 第9回ウィキペディアブンガク体験記」より引用
立項する題材は、グーグルで探しました。はじめに「小津安二郎 and 北海道」「小津安二郎 and マンガ」など、自分が関心のあるトピックと絡めて and 検索をしたのですが、結果は今ひとつ。そこで、小津が著名な映画監督であるということは一旦忘れて、小津安二郎の人となりについて調べようと考えました。具体的には「小津安二郎 and 生活」「小津安二郎 and 食事」「小津安二郎 and 好物」などで検索しました。
すると、小津はとんかつが好きで、蓬莱屋というお店がお気に入りだったと知りました。蓬莱屋について調べてみると、日本で最初にヒレカツを商品化した店という説もあるとのこと。小津のエピソードを抜きにしても、ウィキペディアの求める「特筆性」を満たす題材だろうと感じ、執筆をすることにしました。
Eugene Ormandy
興味深いお話、ありがとうございます。個人的には、グーグルを活用して題材を探すという点が面白いなと感じました。というのも、私自身は題材探しの段階で、検索エンジンをほぼ使わないからです。
「馴染みのない事物についてのウィキペディア記事を堂々と作成する方法」というブログ記事にも書いたのですが、イベントのための記事を作成する場合、私は百科事典をめくりながら題材を探すことが多いです。面白そうな題材があったら、その百科事典を参考文献として活用できますし、百科事典に収録されるということは、それ以上に詳しい資料が存在するということですからね。
調査方法と資料の収集方法
Eugene Ormandy
つづいては、調査方法と資料の収集方法について教えてください。
逃亡者
「各種データベースをウィキペディアの編集に活用する」というインタビュー記事で、ウィキペディアンの Uraniwa さんが紹介していた方法と近いですね。Uraniwa さんは [[蔵の街]] という記事を執筆するために、様々なデータベースを使ったと語っていますが、私も同じです。
Eugene Ormandy
[[蔵の街]] の作成にあたって、色々なデータベースを活用してますね。
Uraniwa
はい。国立国会図書館デジタルコレクション、グーグルスカラー、新聞データベース、大宅壮一文庫の Web OYA-bunko、グーグルブックス、栃木市公式サイト、栃木図書館郷土資料室などを活用しました。
Eugene Ormandy, Uraniwa「各種データベースをウィキペディアの編集に活用する」より引用。
私の場合は、国立国会図書館デジタルコレクション、グーグルブックス、大宅壮一文庫の Web OYA-bunko を活用しました。雑誌記事のデータベースである Web OYA-bunko で、蓬莱屋の記事がいくつかヒットした時は「これはいける!」と思いましたね。また、新聞データベースについては、nifty の新聞・雑誌記事横断検索を活用しました。有料ですが、地方紙も調べることができるので大変便利です。
ある程度資料にあたりをつけたら、図書館で資料を収集します。今回は札幌市の図書館、北海道立図書館を活用しました。また、図書館で集められなかった資料については、国立国会図書館の遠隔複写サービスを活用しました。
実は、蓬莱屋のウェブサイトも調査に大変役立ちました。というのも、蓬莱屋を取り上げた雑誌記事等がまとめられているからです。
Eugene Ormandy
雑誌記事がまとまっているのは嬉しいですね!ところで、記事の執筆にあたってメインとなった資料はありましたか?
逃亡者
『実業の日本』という書籍に収録された、十條四郎の論考「借りた十五圓を資本にして屋臺トンカツ屋から出發 蓬莱屋成功物語」ですね。蓬莱屋の沿革をまとめるのに重宝しました。ただし、1931年発行の古い本ということもあって、蓬莱屋に関する出来事を幅広くカバーしているというわけではありません。
Eugene Ormandy
なるほど。私も [[名曲喫茶クラシック]] や [[名曲喫茶ルネッサンス]] といった、喫茶店のウィキペディア記事をいくつか作成しているのですが、飲食店・喫茶店って「骨格・背骨」となる資料が存在しないことが多いですよね。
逃亡者
そうですね。十條の論考も、1931年以降のことは書いてありませんし。
Eugene Ormandy
ただ、そういった題材にこそ、雑誌専門図書館の大宅壮一文庫は役立ちますよね。雑誌記事という細かいパーツで全体を組み立てられますから。
逃亡者
たしかに。
Eugene Ormandy
ところで、ウィキペディアで禁止されている「宣伝的な文章」にはならないように雑誌記事を活用するのって、結構難しいですよね。飲食店は特に顕著だと思いますが。
逃亡者
難しいですね!今回も苦労しました。特に雑誌記事は「このとんかつはこんなに美味しいんだ!」といった宣伝記事が多いので、ウィキペディアに役立つ記述を抽出・要約するのに難儀しました。
Eugene Ormandy
[[蓬莱屋 (とんかつ店)]] の記事を読んですごいと感じたのは、それらの記述を上手く抽出して、地の文に落とし込んでいるところです。例えば、メニューについて説明した「特徴」節ですね。
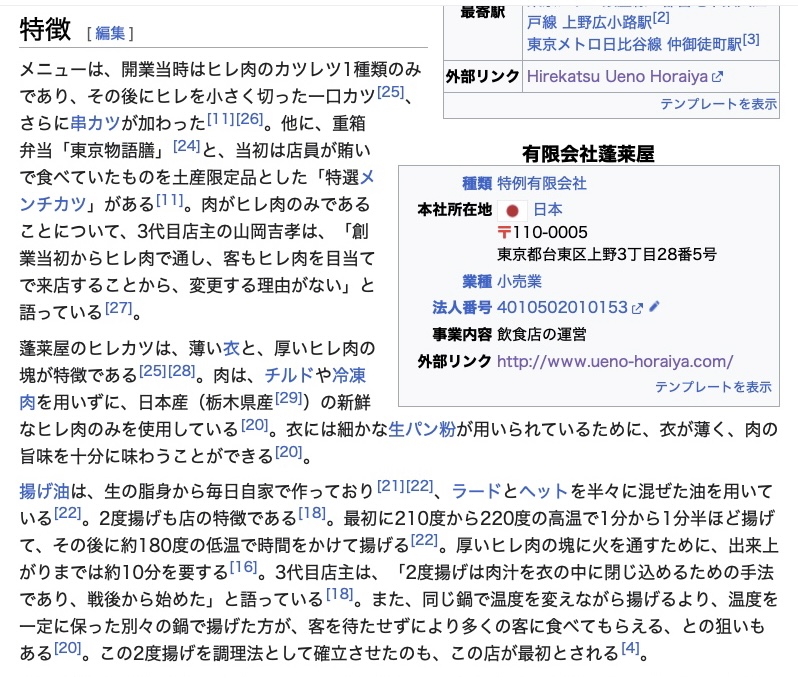
私も食べ物について書くことがありますが、雑誌記事の雑多な記述をウィキペディアの地の文に落とし込めるほどの文章力、要約力はないので、引用という形で済ませてしまうことが多いですね。[[フルーツサンド]] という記事を書いた時もそうでした。
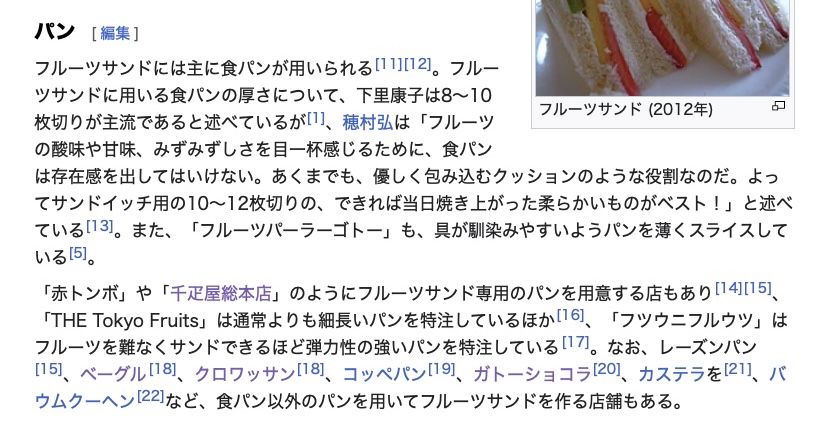
改めて、逃亡者さんの文章力・構成力を見習わなければ…..と感じました。
章立てをどのように決めたか
Eugene Ormandy
[[蓬莱屋 (とんかつ店)]] の章立てはどのように決定されましたか?
逃亡者
現時点(インタビュー時に参照したのは 2023年5月19日 (金) 23:24 (UTC) 版)では、「沿革」「特徴」「著名人による評価」「創作作品での扱い」という章立てになっていますが、下書きに着手した段階からこの構成にしようと決めていたわけではありません。
まずは蓬莱屋に関する情報を下書きに列挙し、ある程度長くなったら章を分けるという方法で執筆を進めました。なお、私は他にもいくつか飲食店記事を書いていますが、 [[キッチン友]] 程度の長さであれば、細かく章を分けることはしませんね。
ちなみに、先日ウィキペディアンの Takenari Higuchi さんと対談した際、記事のリード文を書くタイミングについて「ケースバイケース」とお話ししましたが、今回ははじめに「蓬莱屋は、日本の食堂」という冒頭の一文を書いたのち、リード文以降の内容を充実させ、最後にそれらの中から重要な情報を抽出して、リード文の2文目以降に反映させました。
Takenari Higuchi
私からも質問させてください。逃亡者さんは記事のリード文について、下書きを完成させてから書き上げますか?それとも最初に書き上げてから中身を埋めていきますか?
逃亡者
あまり考えたことはありませんが、ケースバイケースですね。新聞や伝記などで良いリード文がある場合はそれを参考にしますが、何もない場合は自分で書かないといけないので、かなり悩みますね。
Takenari Higuchi
リード文の作成は難しいですよね。私は下書きを完成させてから、リード文を作成するタイプです。なお、私は逃亡者さんの記事のリード文をよく参考にしています。
Eugene Ormandy「【対談】ウィキペディア編集者が考えていること」より引用。
どのように評価をまとめたか
Eugene Ormandy
[[蓬莱屋 (とんかつ店)]] の記事には「著名人による評価」という節がありますが、様々な人の評価をまとめるにあたり、意識したことはありますか。
逃亡者
やはり小津安二郎関連の評価が多かったので、冒頭に書きました。その後、他の著名人による評価を並べています。なお、雑誌のグルメ記事には、そこまで著名ではない方のコメントもありましたが、それらはカットしました。また、否定的な評価については、そもそも見当たりませんでした。まあ、飲食店を紹介する記事で「この店はマズい」と書くものはあまりないですからね。
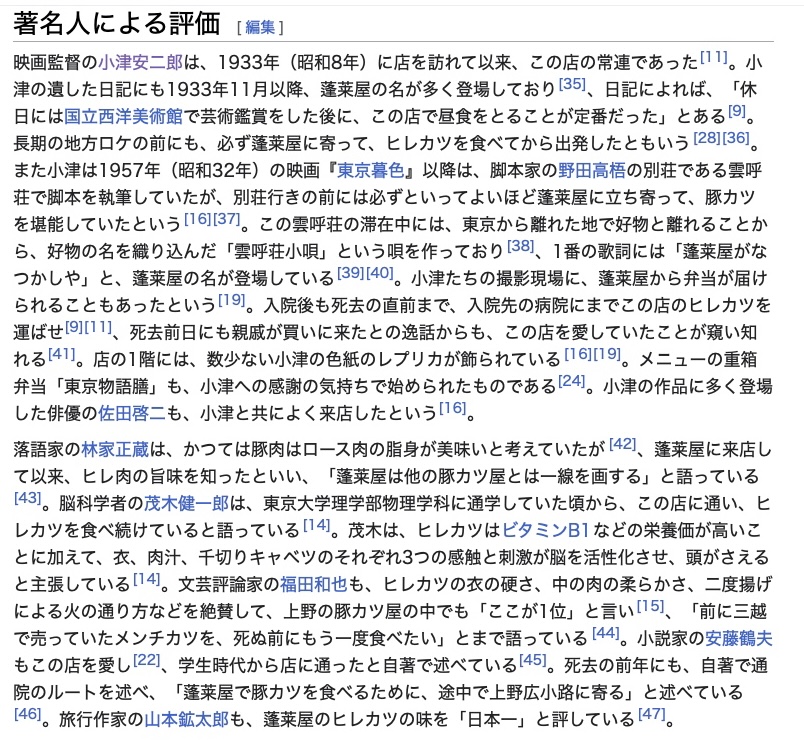
Eugene Ormandy
たしかに、人物などに比べると、飲食店は「否定的な評価」があまり存在しないトピックと言えますね。
書かなかったもの
Eugene Ormandy
ウィキペディアの記事に書けなかったもの、もしくは意図的に書かなかったものはありますか。
逃亡者
蓬莱屋のウェブサイトで紹介されていた、香港の雑誌記事は活用しませんでした。私は日本語以外ほとんど読めませんので。
また、資料が見当たらなかったために書けなかった記述としては、屋台から店舗へと以降する経緯ですね。店舗を構えられたということは、それなりに繁盛していたからだと推察できますが、そのような記述のある資料は見つけられませんでした。
北海道在住のため、実際の店舗の写真を撮影できなかったのも残念ですね。お店の外観の写真は、Flickr で公開されていたので、ウィキメディア・コモンズにエクスポートしたうえで記事に活用したのですが、実際のとんかつの写真はありませんでした。[[珈琲文明]] くらい、写真を充実させたかったですね。
Eugene Ormandy
上野に行く機会があれば、撮影しておきますね!
その他感想
Eugene Ormandy
その他に何か、感想などはありますか?
逃亡者
実は、私は豚肉が苦手なんです。なので、記事を書いている最中に、少し気持ち悪くなることもありました。ちなみに、苦手な食べ物に関する記事は他にも執筆しています。良質な記事にも選出された [[小樽あんかけ焼きそば]] です。
Eugene Ormandy
こんな共通点があったのか!と驚いているのですが、実は私も嫌いな食べ物の記事を執筆しています。具体的には [[フルーツサンド]] ですね。こちらも良質な記事に選出していただいたのですが、私はフルーツが大の苦手でして、材料について書いている時は、非常に暗い気持ちになりました(笑)
逃亡者
嫌いなトピックだからこそ、あまり執着せずに書けるのかもしれませんね。[[Wikipedia:エチケット]] にも「あまりにも情熱を持っている事柄については執筆を避けてください」と書いてありますし。
Eugene Ormandy
なるほど!
逃亡者
あとは、孤立の解消、すなわち他のウィキペディア記事に蓬莱屋の記述を追加して、[[蓬莱屋 (とんかつ店)]] の記事とリンクさせるという作業に少し苦労しました。結局、[[小津安二郎]] という記事と [[豚カツ]] という記事にリンクさせました。
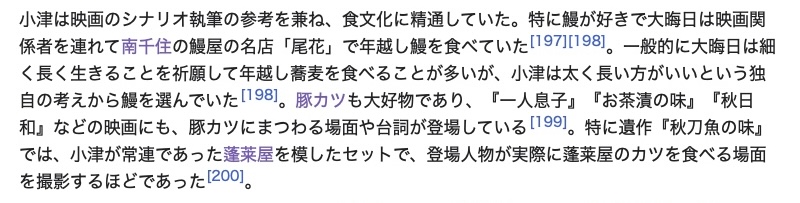
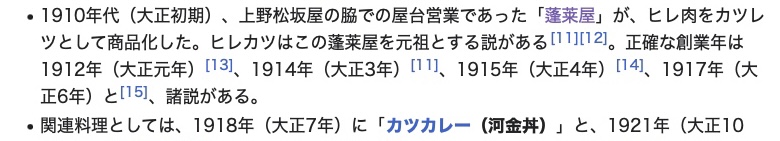
ちなみに [[CADOT]] という洋菓子店の記事を作成した時は、[[マドレーヌ]] という記事にリンクさせました。
Eugene Ormandy
特殊なトピックほど、孤立の解消って難しいですよね。私は「関連項目」節に追加して済ませてしまうことも多いです。
逃亡者
それも一案ですよね。ただ、私はガイドライン [[Wikipedia:関連項目]] の「本来、内部リンクは本文記事内の文中に包括されるのが理想的」という記述ももっともだと思うので、できる限り記事に組み込みますね。
Eugene Ormandy
逃亡者さんの執筆の裏側や、考えていることについて伺えてよかったです。大変勉強になりました。本日はどうもありがとうございました!
まとめ
日本語版ウィキペディアを代表する優良執筆者の1人である逃亡者さんに、インタビューを行いました。編集する記事を決定する方法から、執筆テクニック、さらには執筆哲学まで幅広くご教示いただき、感謝の念に堪えません。逃亡者さん、本当にありがとうございました。
本稿が、執筆スキルを向上させたいと考えているウィキペディアンや、ウィキペディアに関心がある研究者・ジャーナリストのお役に立てば幸いです。

Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?
Start translation