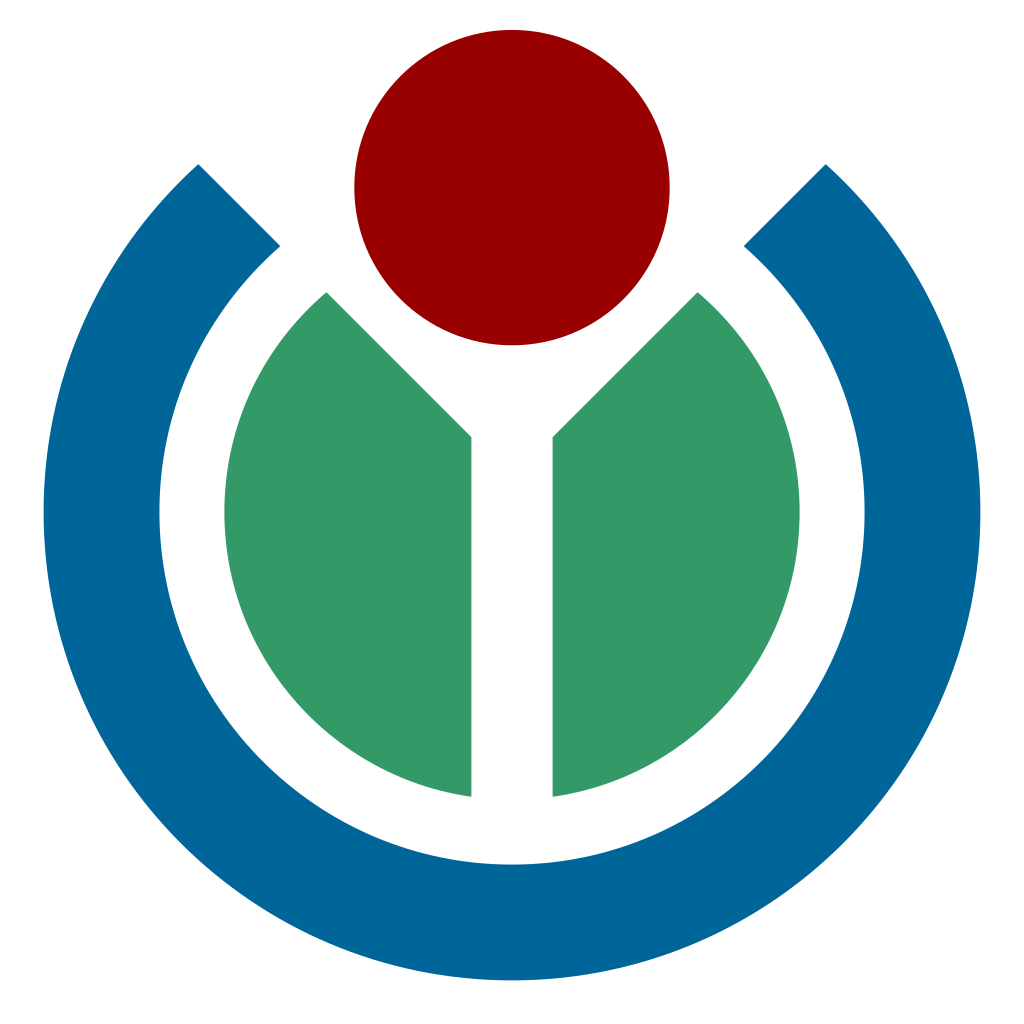東京23区の公共図書館をウィキペディアの編集に活用するシリーズ第12弾。今回は豊島区立池袋図書館を訪問しました。
執筆にあたって
図書館の意義が問われる時代です。出版不況が続き、オープンアクセス化が推進され、人工知能が台頭する現代において、図書館はどのような存在であるべきなのでしょうか。
それを探るためには、図書館の活用記録、すなわち「図書館のおかげでこんなことができた」という記録が、様々な観点から作成される必要があると私は考えています。未来を描くためには過去を知る必要がありますし、過去を知るためには資料が必要だからです。
そのような思いで「東京都の公共図書館をウィキペディアの編集に活用する」シリーズを立ち上げました。このシリーズでは、私 Eugene Ormandy が東京23区の様々な公共図書館を訪問し、その資料を活用してウィキペディアを編集する模様を、ウィキメディア財団のブログ Diff にまとめます。
本シリーズが、図書館の意義や未来を探るための参考資料となれば幸いです。
事前準備
編集するトピックは、池袋図書館が作成しているパスファインダーから探すことにしました。具体的には、池袋図書館のウェブサイトに掲載されている『ふくろう通信』2020年9月号に目を通し、豊島区立郷土資料館について編集することに決めました。
図書館訪問
池袋駅で下車し、15分ほど歩いて池袋図書館へ。繁華街から少し離れた、落ち着いた場所にあります。

入口にはチラシが置いてありましたが、他の図書館に比べて種類は少ないかなと感じました。また、入口横には、江戸川乱歩の特集や、東京都地域資料の棚がありました。郷土資料が入口に置かれているのは、珍しいなと感じました。
1階の書庫をぶらぶらしたのち、2階の「こどもの本・資料コーナー」へ。階段を登ってすぐ、教育関連のチラシが置かれていました。上池袋図書館を訪問した時のレポートにも書いたのですが、チラシを一箇所に集中させず、「このチラシはどのような人が必要としているのか」を考えて、様々な位置に置くのはとてもいい試みだと思います。
ただし、残念だったのはエレベーターがなかったこと。こればっかりは建物の都合なので仕方がないのですが、改善を期待したいですね。
いつもどおり、私が愛してやまないプロレス本のコーナーも確認。私が訪問した時は、7冊ほど置かれていました。『別冊宝島1248 格闘技 & プロレスマット界あの舞台裏が知りたい』のような、いわゆる暴露本があるのは珍しいなと思いつつ、『井田真木子と女子プロレスの時代』に目を通しました。
閑話休題。泣く泣くプロレス本を棚に戻し、1階のレファレンスカウンターで「豊島区立郷土資料館の歴史に関する記述がある本はありますか」と尋ねました。「しばらくお待ちください」と言われたので、閲覧コーナーで新聞を読みながら待機していたところ、数分後に郷土資料館の紀要や年報を紹介してもらいました。
その後、2階の机で資料を読みながら、ウィキペディア記事に使えそうな記述をピックアップ。有用な記述を全て収集しようとすると、かなり時間がかかると感じたので、開館前史の情報のみピックアップしました。なお、その場でウィキペディア記事の編集は行わず、スマートフォンのメモに情報を記入しました。
結局、図書館を訪問した数日後に、メモに基づきウィキペディア記事 [[豊島区立郷土資料館]] を加筆しました。差分はこちら。
まとめ
丁寧なレファレンスを行っていただき、とても嬉しかったです。エレベーターがないという欠点はありましたが、これは今後の行政に期待したいところです。

Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?
Start translation